岡山ママブロガーのマイコです。
元小学校教諭です。
長女が小学3年生です。
コロナ休校期間中の家庭学習のお役に立てればと思い、家庭で簡単にできる親子レッスン案を紹介しています。
今日は、理科です。
何のたねを育てるのか決めよう

まずは親子で何の種を育てるのか相談して決めましょう。
種類は違いが比較できるように2種類以上がいいです。
我が家は家庭菜園があるので、ニンジン、サニーレタス、ホウレンソウ、しゅんきくなど、いろいろ植えていますが、プランターで栽培できるものを選ぶとお世話も簡単でいいですね。
子ども用のプランターを買い、それぞれ好きなものを選ばせて育てています。
自分の!というのが嬉しくて、成長が自然と気になるし、かわいいみたいですね。
教科書にはホウセンカやヒマワリが紹介されていますね。
これは、成長したあと、またタネができるようすがよく分かるからでしょうね。
オクラもピーマンも、タネが分かりやすいですね。
そういうものを選ぶのもいいと思います。
我が家はハムスターを飼っているので、またとうもろこしやヒマワリを植えようと思っています。
たねクイズをしよう!

タネを植える前に、たねクイズをすると面白いですね。
だいたいタネは袋売りだと思うので、子どもに見せる前に少しだけ取り出し、たねクイズをすると面白いです。
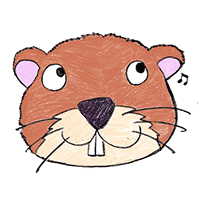
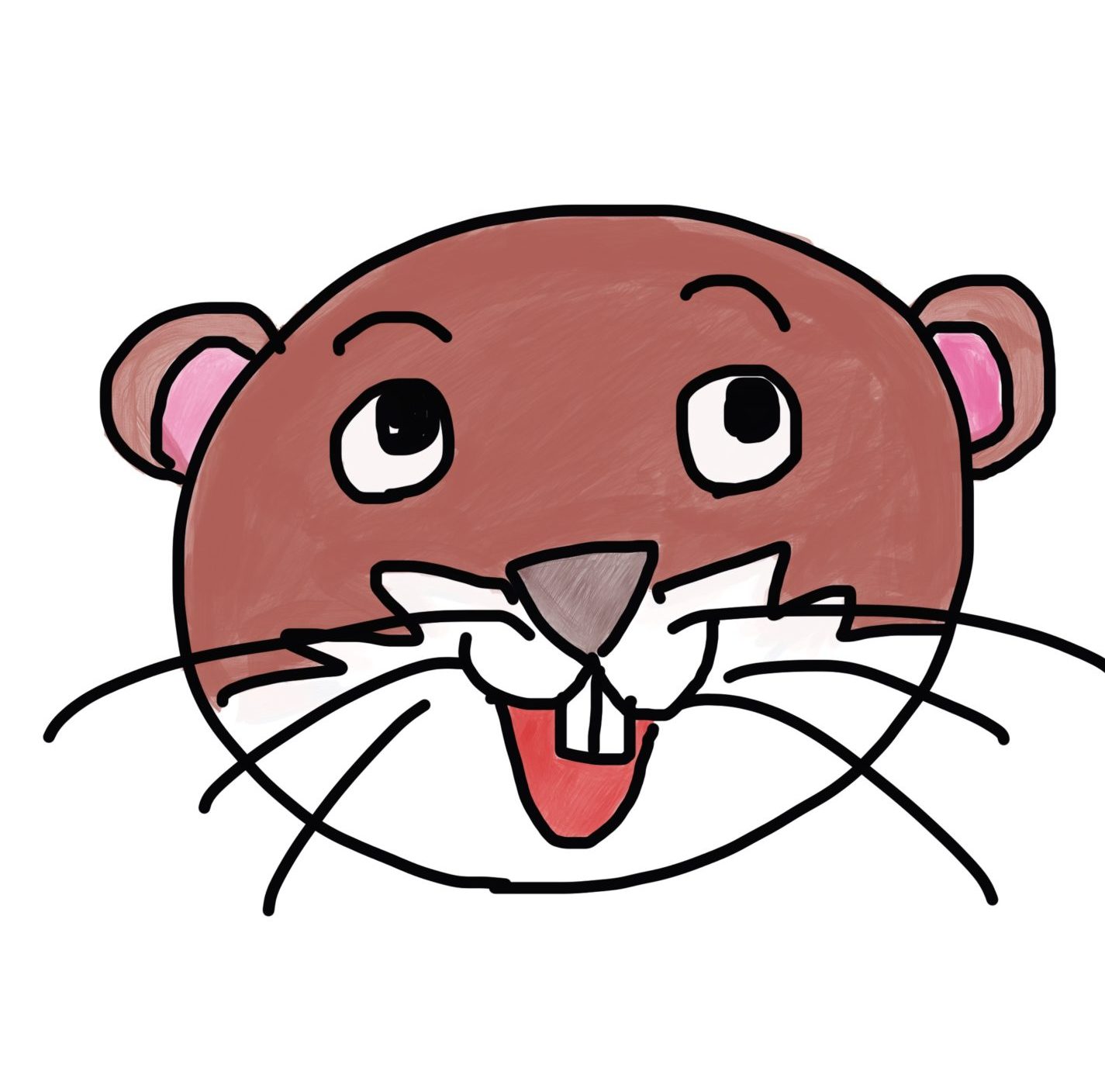
…。
うちの畑にうえたやつ?
ん~、わからん。
キャベツとか?
まぁ、よっぽどわかりやすいのでないと、分かるわけがないんですけどね(笑)
タネの形や色から何が育つか予想することは、これから先の観察にもつながり、いい導入になると思います。
たねの観察カードを書こう
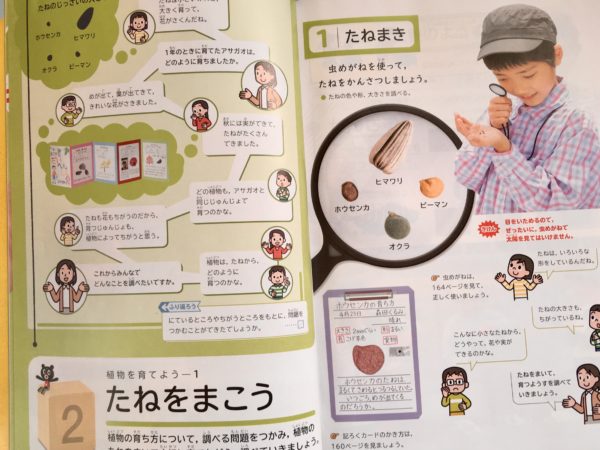
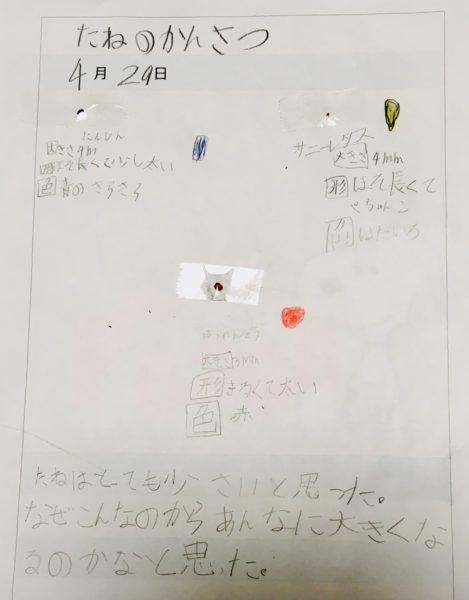
もも子のタネの観察カード。左上)ニンジン 右)サニーレタス 下)ほうれんそう
- にんじん
- サニーレタス
- ほうれんそう
それぞれのタネを虫メガネで観察します。
タネには色が付けてありました。
これはタネを間違えないようにするための工夫で、自然な色ではないことを教えてあげました。
- 色
- 大きさ(測って記録する)
- 形
- 天気
- 気が付いたこと、思ったこと。
たねを植えよう
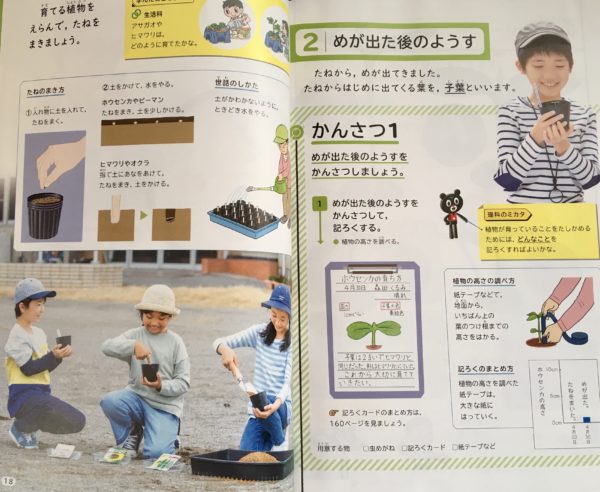
この単元ではしばらくの間は種から植物を育て、その成長の記録を観察カードに書いていく活動がメインです。
幼稚園でも野菜や花を育ててきましたね。
2年生までの生活科でも朝顔やミニトマトを育ててきました。
今までは苗でしたが、今回はタネです。
教科書p.18に乗っている『たねのまき方』を参考にしながら一緒に植えましょう。
- たね
- プランター
- 花・野菜の土
- 水はけ用の砂利・ネット等
- 肥料
- スコップ

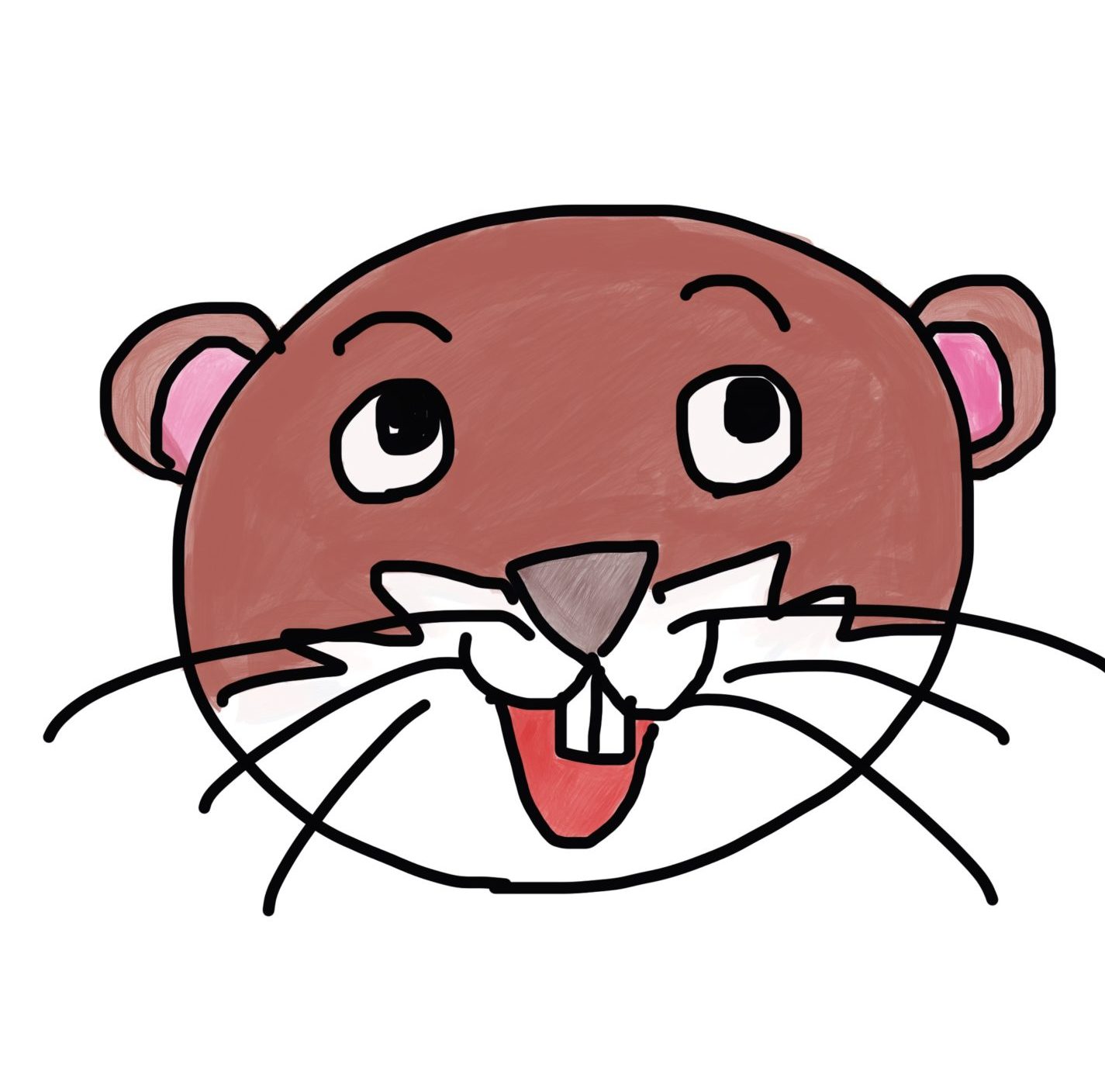
お母さん、もも子のニンジン、全然芽が出んよ。ダメだったんかな?
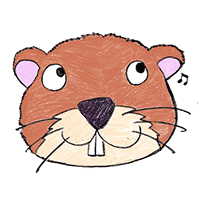
ん~、どぉだろうねぇ、今、土の中でがんばってるんじゃない?
なかなか芽が出なくて心配するもも子。
トトロのめいちゃんみたいでした(笑)
気長に芽が出るのを待ちましょうね~(*´ω`*)
我が家は、たまたま3月に休校期間が少しでも楽しくなるようにと思って、それぞれのプランターを買い、ニンジンのタネ、、じゃがいも(芽が出てしまった種芋を活用)、トマトの苗(希望で購入)を理科とは関係なしに植えていました。
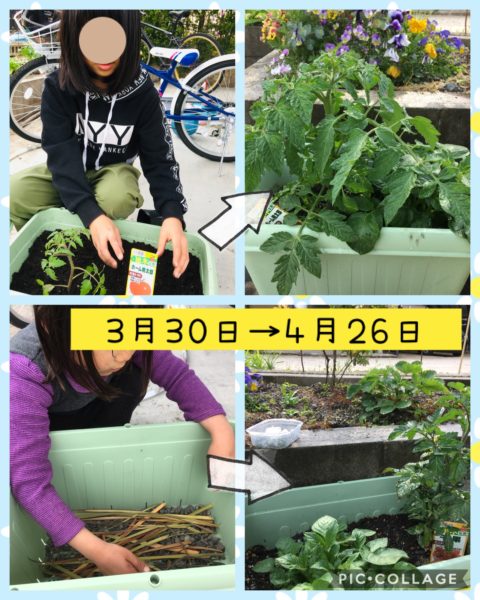
なので、タネの観察カードは教科書が配られて、理科の勉強を一緒にやり始めた後から書きました。
ちょうど今、一か月ほどたって、芽が出てきたところだったので、そのまま観察に入りました。
成長の記録を書こう
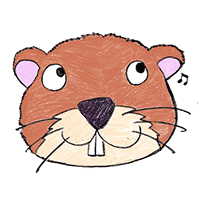
変化が分かるようにかんさつカードを書くには、どんなことに気をつけて書いたらいいかな?
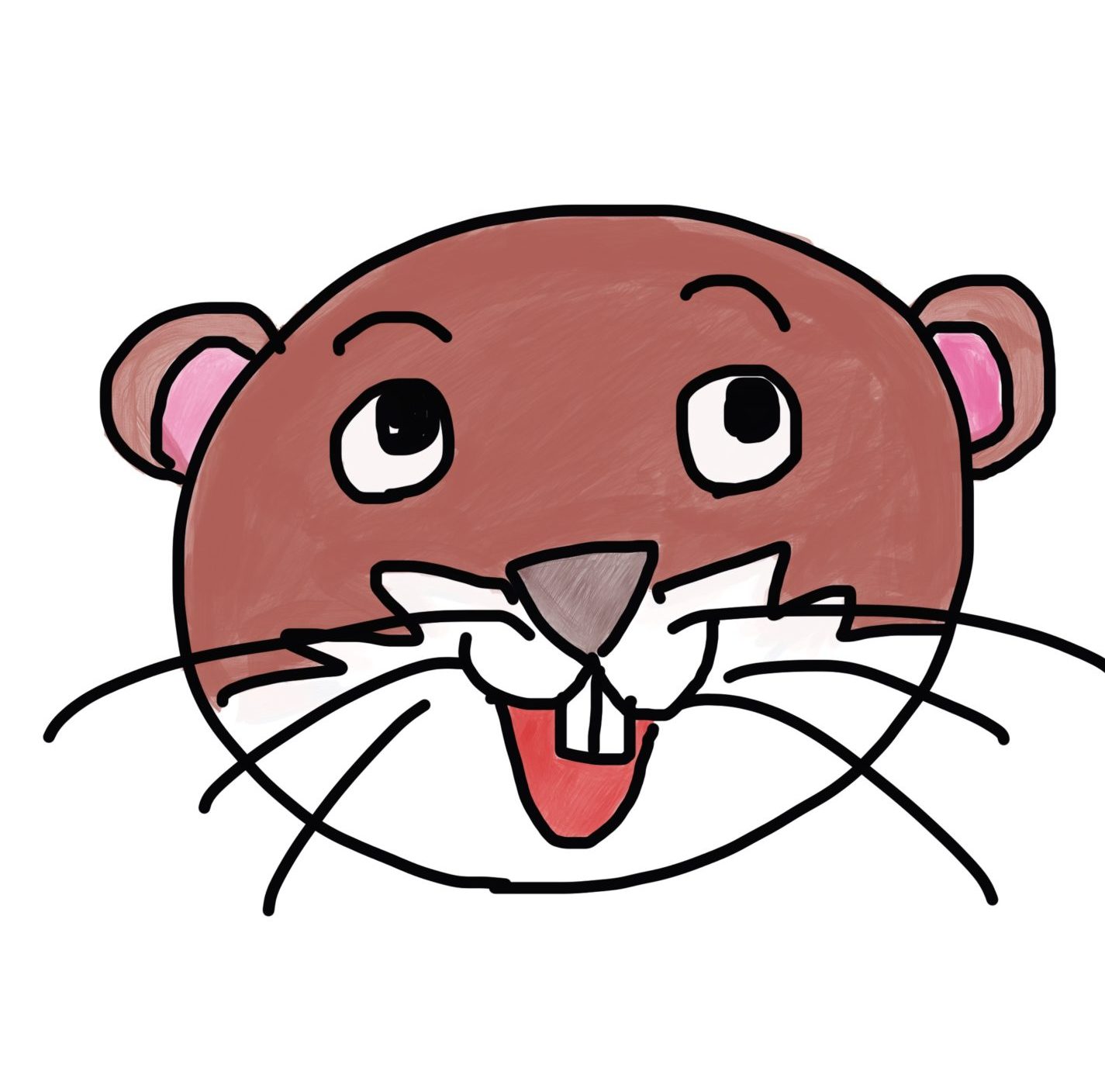
どのくらい大きくなったか。
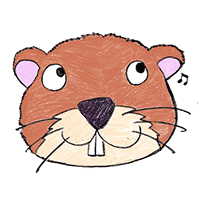
どうやったらそれが分かる?
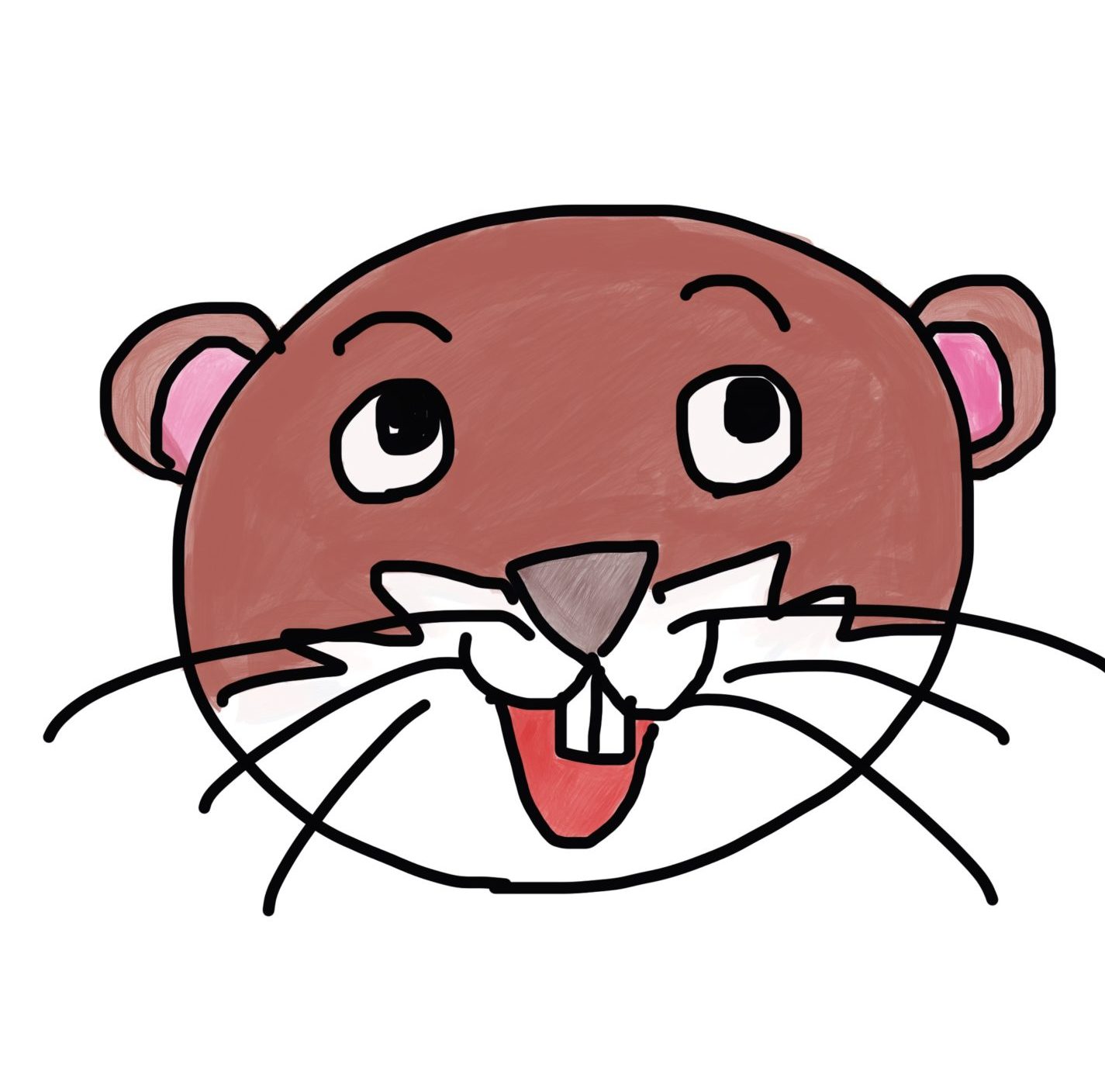
葉っぱの数とか、花がさいたとか、何センチかとかを書く。
かんさつの視点を考えさせてからカードを書きます。
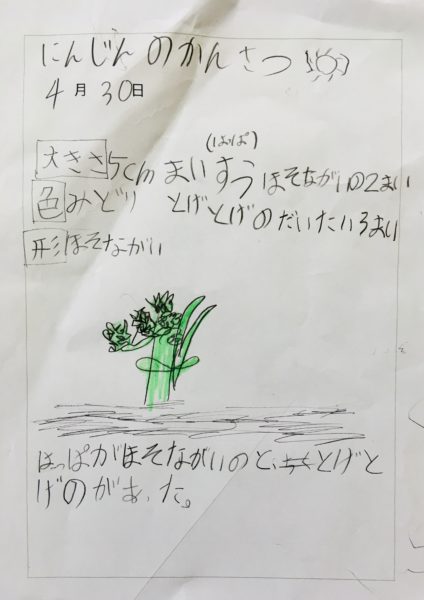
ニンジンの観察カード
最近、春の生き物とモンシロチョウの観察でかんさつカードばかり書いているから、ちょっと飽きています(笑)

かんさつ2日目の様子。
家庭学習は楽しくしたいので、あまり細かいことは言わずに書かせています。
んでも、子葉は書いてほしかったなぁ…。
また機をみて声をかけてみようと思います。

サニーレタスの成長の様子(同日撮影)
家庭菜園では、サニーレタスが徐々に芽をだしているので、成長の過程を畑でそのまま見比べることができます。
一緒に観察しながら、一番初めに出てくる芽のことを子葉(しよう)ということを教え、大きくなった苗の下側をめくると、そこにはずっと子葉が残っているのを一緒に見ました。
そして、
- 子葉は他の葉とは形も大きさも全然違うこと
- ニンジンの子葉は細長くて草のようだったけど、サニーレタスの子葉は丸っこいこと
- どちらも2枚であること
を確認しました。
ついでに、どうせ学ぶことになる、本葉(ほんば)という言葉も教えました。
他にもしゅんきく、ホウレンソウ、カイワレ大根もかわいい芽をだしています。
ちょうど今、観察できてラッキーでした。
教科書p.20にたくさんの子葉の写真が出ているので、教科書の写真をみて再確認するといいですね。
学びの順序
- 親子で何を育てるか決める(比較できるように2種類以上がよい)
- タネを虫メガネで調べる。
- タネを植えて育てる。
- 大きさ・色・形に気をつけて観察カードに調べたことを書く。
- 成長の過程で自分が思ったことも観察カードに記録する。
- それぞれの違いや似ているところを探す。
- 子葉という言葉を知る。
- どの植物も、子葉の数は2枚であることに気づく。
- にているところ、ちがうとこをを話し合う。
まとめ

家庭菜園で育つ植物たち。
それにしても理科はひたすら観察ですね…。
あおむしと植物のカード2枚を書くので、もも子はだんだんめんどくさくなってきました(/ω\)
親もちょっとめんどくさ……。
ちびまるこちゃんで、まるちゃんたちが豆電球の実験をしているのをみて、
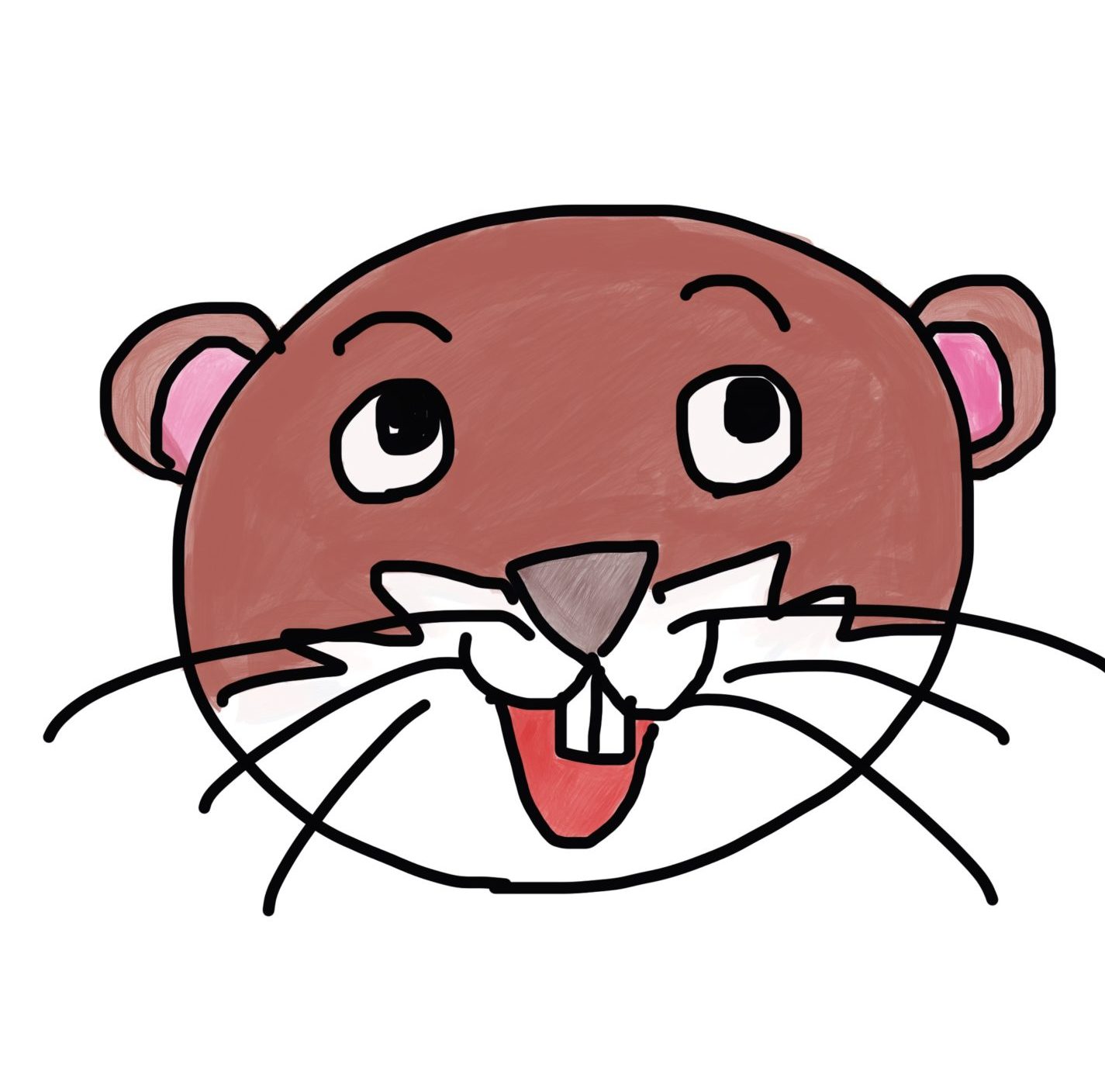
ああいう実験がやりたい!
言い出しました(笑)
休校も一か月延びたし、ちょっと気分転換しながら進めていきたいなと思います。

プランターでじゃがいもはムリじゃない?
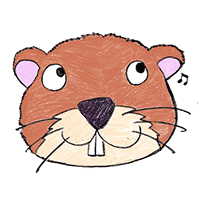
…。




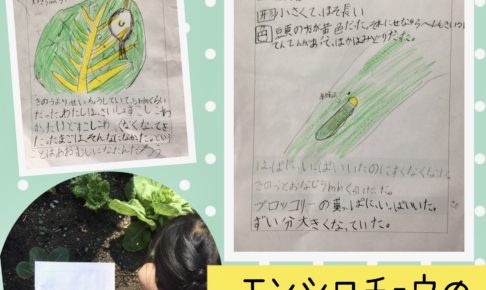
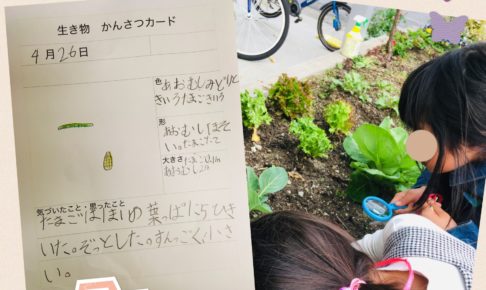

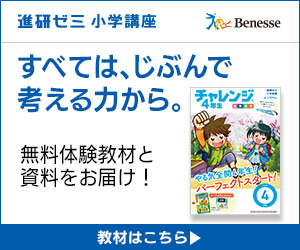

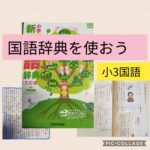


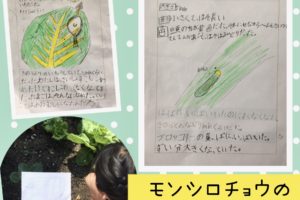
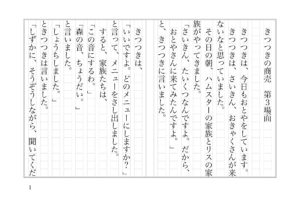
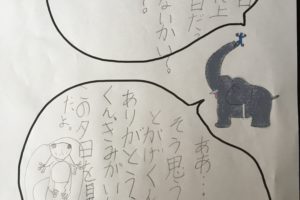



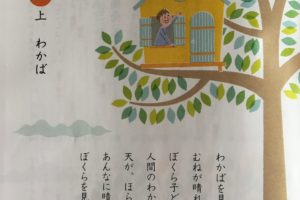
たねクーイズ!
このタネは何の種でしょう?